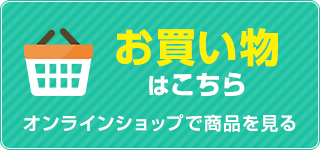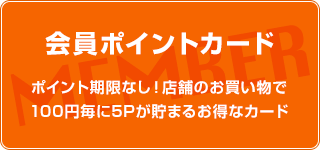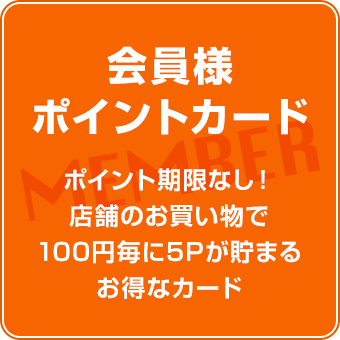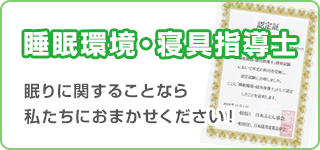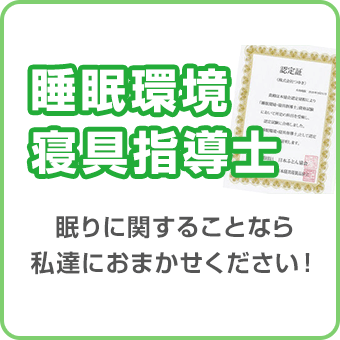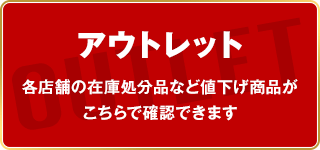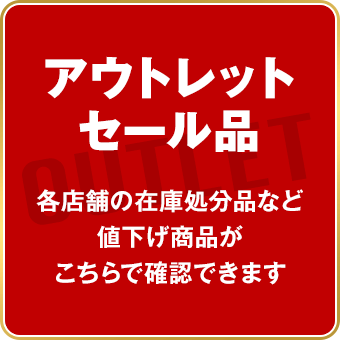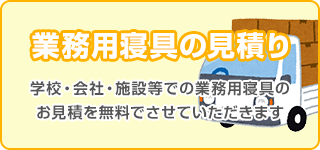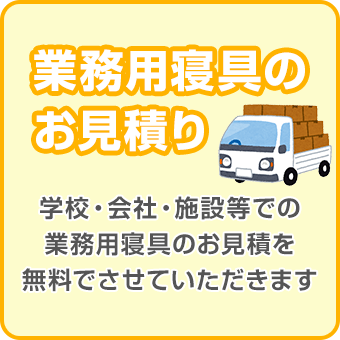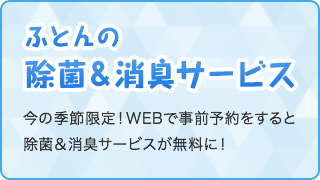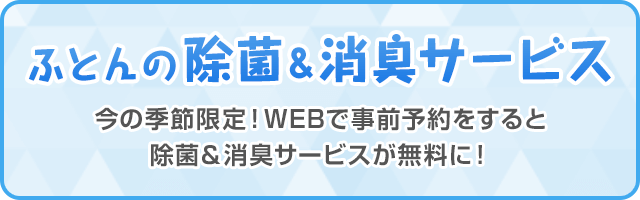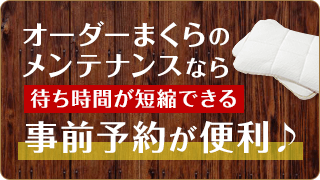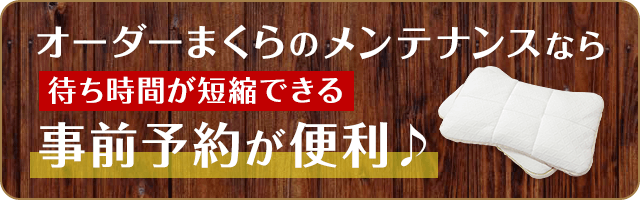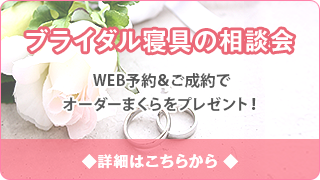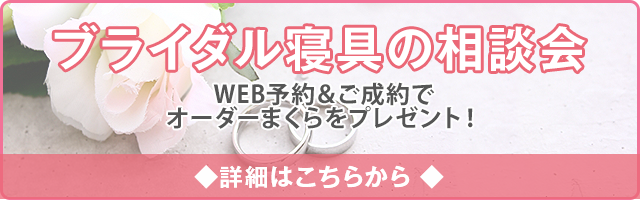2024年4月11日
いつも「ふとんのつゆき」のホームページおよびオンラインショップをご覧いただき、ありがとうございます。
誠に勝手ではございますが、EC事業部では社員研修のため、下記日程は電話&メール応対と出荷業務は臨時休業とさせていただきます。
尚、お問い合わせメールとオンラインショップへのご注文は24時間自動受付となっておりますので、臨時休業中の受付分は4/19(金)より順次対応させていただきます。
お客様にはご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承の程、よろしくお願いいたします。
■EC事業部
・2024年4月18日(木)臨時休業
※臨時休業はEC事業部のみです。実店舗は全店通常通り営業しております。